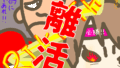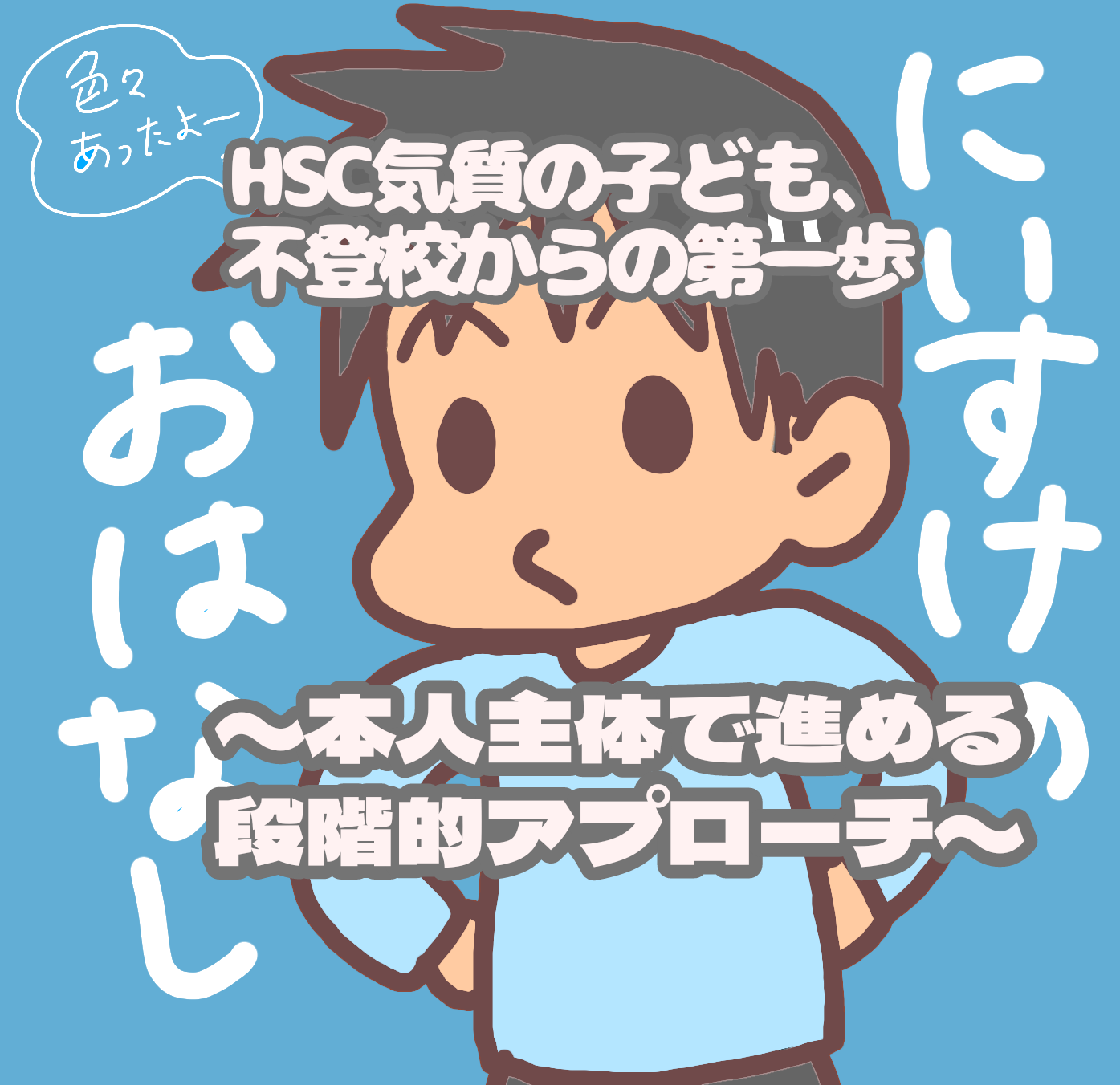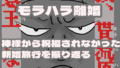「不登校になった子どもにとって、どんな支援が一番大切なんだろう?」
私は長男が学校に行けなくなってから、ずっとこの問いに向き合ってきました。
制度や支援先の情報はあふれているけれど、本人の気持ちと合わなければ意味がない。
そう気づかされた体験を、今日は書いてみたいと思います。
不登校の子にとって「支援」とは?制度と親の迷い
長男が不登校になってから、私はいろんな支援を探してきました。
メンタル系医療(成人)従事者なので、職場の心理師さんや、精神保健福祉士さんに相談したり情報収集をする日々。そんな中、居住地では不登校児も放課後等デイサービス(以下デイサービス)の利用対象になる。という情報。
利用者の子が、デイサービスで活動を続けることで笑顔を取り戻し、楽しく通所していること等、魅力的な話を聞くことが出来、ますます惹かれる私…。
利用には、主治医の診断書(放課後等デイサービスの利用が望ましいという文書)が必要だとのこと。善は急げ!早速支援センターに相談依頼し、デイサービスの見学を申し込み、かかりつけ医への受診予約を済ませました。
小児心身症外来にはしばらく通ってはいるけれど、先生からサービス利用を提示されたことはありませんでした。
診察の場で、利用可能だと言われたこと・利用出来るなら利用してみたい旨…先生は耳を傾け、ウンウンと頷いてくれましたが、
👨⚕️ 医師
「にいすけくんはどう? 行ってみたいの?」
「放課後等デイサービスは、発達障害の診断がついた子しか利用できないよ。」
「デイサービスには、不登校の子の勉強を専門に見てくれるスタッフはいないからね。」
と言われました。役場からそう伝えられているそうです。どんなに居住地では利用出来ると言われたことを伝えても、先生の首が縦に振られることはありませんでした。
一方で、支援センターの職員さんからは
🏢 支援センター
「不登校児も対象だから利用できるよ」
と言われていました。
同じ制度を見ても、市町村によって解釈が違う?
じゃあどうすればいいの?💦
と親として混乱したのを覚えています。

ただ、それ以上に大きかったのは――本人の「行きたくない」という気持ち。
見学を本人に打診する際にも、「嫌」と言っていましたが、正直「埒が明かない」という思いも捨てきれず、「とりあえず見てみないと分からないから、見るだけ見てみよ!」と半ば無理強いして決めたのでした。
しかし、かかりつけ医の先生は対象では無いとバッサリ。不登校児専門医である先生からそう言われると…
デイサービスに行く・行かないの前に、本人の心の安全が最優先にしないといけないと感じました。
📝不登校の児童が放課後等デイサービスを利用する手順や注意点 – 放課後等デイサービス ココノワ
↑こちらの記事では、不登校児がデイサービスを利用するのに必要な条件について触れています。障害福祉サービスなので、【受給者証】が必要なのだそうです。
かかりつけ医や自治体は、この部分がにいすけは非該当だと言いたかったのかな、と推察されます。
📝受給者証とは?申請・取得の方法や使い方などを解説します – ことばの教室 そらまめキッズ
HSC気質と「未知の場所」への不安
長男はHSC(Highly Sensitive Child)の特性が強く、初めての場所や得体の知れない場所に強い不安を感じます。
これは、ただの「わがまま」や「甘え」ではなく、脳や神経の働きが敏感であるがゆえに起こる自然な反応。
私自身も「よく知らない場所」に行くのは緊張するタイプなので、長男の気持ちはよくわかります。
だからこそ、無理に外へ押し出すのではなく、本人が安心できる枠組みを作ることを大切にしたいと思いました。
長男が立てた「段階的プラン」
そんな中で、デイサービスを利用しないとなるなら、これからどうステップアップしていくか。を話し合いました。
にいすけにステップアップしたいという意思があること・通学を目標にせず、将来的に社会で生きやすくする為に、安心して行動出来る【安全地帯】を広げる必要がある。ステップアップはそれを目指してるんだよ、と双方確認。
本人が「こうやってやってみたい」と話してくれたプランがあります。
正確には私が提案したことも多いのですが(笑)、本人が「自分でやる計画」として受け止めてくれたのは大きな一歩です。
🖍 長男の「できた!」を積み重ねる4ステップ
- ホワイトボードに「やること」を書く
その日にやること(勉強や読書など)を可視化する。 - 「できたこと」を付箋にして貼る
一日の終わりに「特に頑張ったこと」を付箋に書いて、ホワイトボードのカレンダー部分にペタリ。 - 月末にノートにまとめる
溜まった付箋をノートに貼り替えて「こんなにやった!」と振り返れるようにする。 - 外出の段階的チャレンジ
・天気の良い日は図書館に行って勉強する
・慣れてきたら、中学校近くの発達支援教室に“挨拶だけ”して帰る(登校扱いになる)

親としての迷いと決断
正直に言えば、「このままでいいのかな?」「遠回りじゃないかな?」という不安はあります。
制度を使えばもっとサポートしてもらえるのかもしれない。
でも、外からの支援に本人が心を閉ざしている状態で無理に連れて行っても、きっと逆効果です。
だから私は、本人の頑張りを尊重し、まずは自分のペースでやってみることを選びました。実を言うと、かかりつけ医で受けた【WIS4C検査】の結果を見て、職場の心理師さんからアドバイスを貰ったのも影響しています(いずれ書こうと思います)。
たとえ遠回りでも、自分で考えた方法を一歩ずつ試してみることで、本人の自信につながると信じています。
今月の小さな挑戦
そして今月の平日休み、長男と一緒に発達支援教室へ“挨拶だけ”行ってみました。
滞在はほんの数分です。
「知らない場所に行った」「ちゃんと挨拶ができた」――それだけでも十分な成功体験。
帰ってきたら、その日もまた付箋に「発達支援教室に行けた」と書いて貼ります。
きっと月末に見返したとき、「自分はここまでやれたんだ」と感じられる材料になるはず。
まとめ
不登校の子どもに必要なのは、必ずしも“外部の支援サービスに通うこと”ではないと思います。
もちろん制度や支援は助けになります。
でも、それ以上に大切なのは、本人の意思を尊重しながら、自分のペースで「できた!」を積み重ねていくこと。
ホワイトボードと付箋、図書館、そして「挨拶だけの訪問」。
その小さな積み重ねが、長男にとって次のステップへの力になっていくと信じています。
あなたなら、子どもの“不登校の第一歩”をどう支えますか?
❀moyu❀
医師対応のサービスもあり、心療内科や精神科の受診を迷っている方にも安心です。
継続的にカウンセリングを受けたい方と、目的に応じて使い分けられるのも良いなと感じました😊

定額制で利用しやすく、継続的に心理サポートを受けたい方におすすめです。
医師対応はありませんが、心理師による丁寧なサポートが受けられます😊