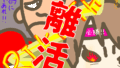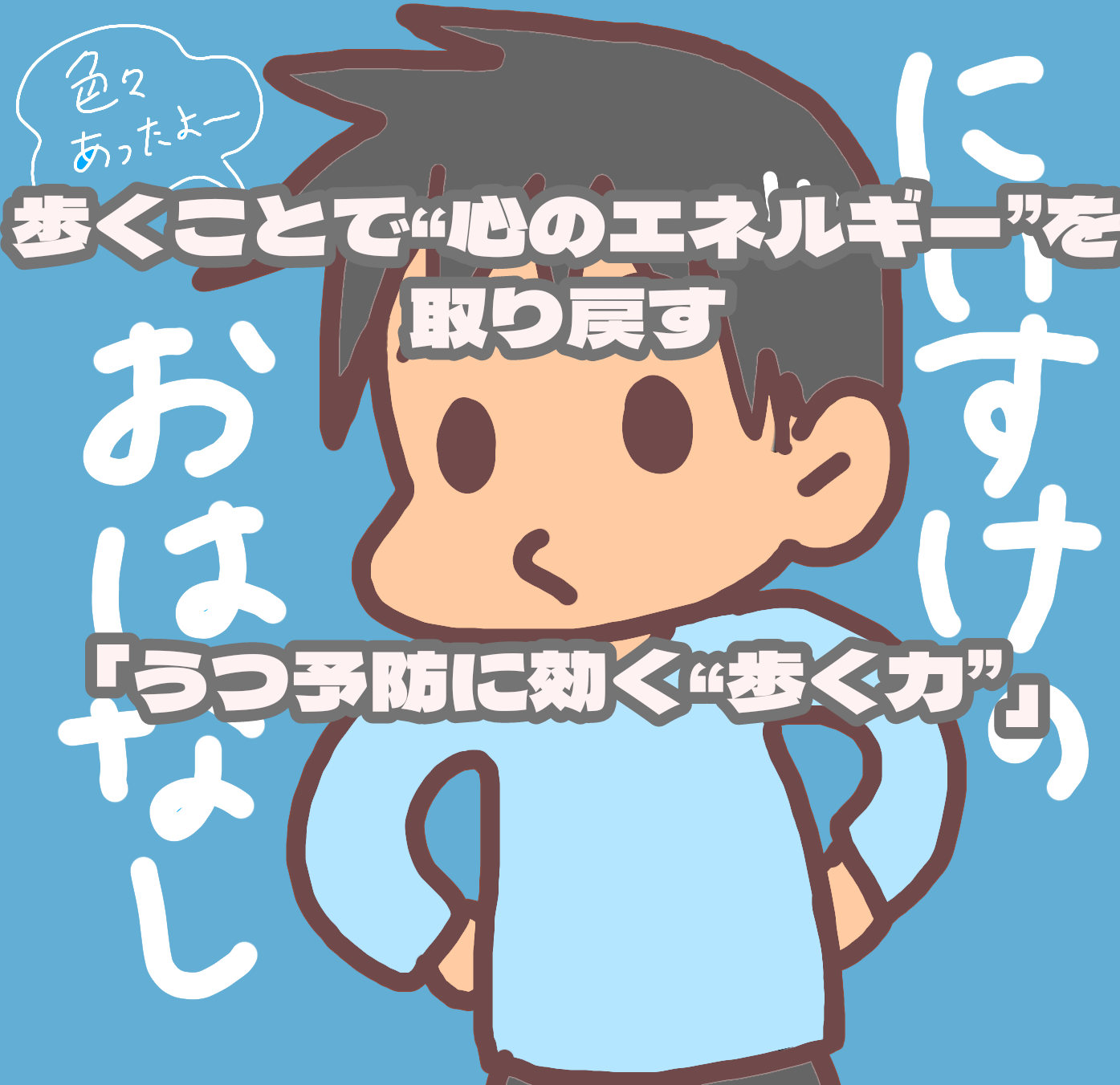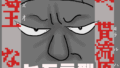はじめに
心が弱っているとき、人は“外の世界”から自分を切り離してしまいます。
抑うつが酷いときには、まずは休息が必要。
エネルギーが切れているなら、無理に動かず、しっかり休みましょう。
そして、少しだけ心と体が動き出す頃——
「外の光を感じたい」
「少し歩いてみよう」
と思える瞬間がやってきます。
その小さな一歩こそ、回復のサインです。
私たち親子も、その“最初の一歩”から変わり始めました。
歩くたびに季節の風や鳥の声が、心に“生きる感覚”を少しずつ取り戻してくれたのです。
🧠 なぜウォーキングがうつ予防に有効なのか
1️⃣セロトニンの分泌を促す
太陽光を浴びながら歩くと、脳内のセロトニンが活性化。
自律神経が整い、気分の安定や睡眠リズムの改善につながります。
#メンタルケア #セロトニン活性
2️⃣リズム運動でストレス緩和
ウォーキングは呼吸と歩調を合わせるリズム運動。
扁桃体(不安中枢)が落ち着き、“考えすぎる脳”を休ませます。
#ストレスケア #リズム運動
3️⃣「出来た」という自己効力感
たとえ5分でも、「歩けた」という事実が、
小さな達成体験となり、自己肯定感を育てます。
#自己肯定感 #小さな成功体験
🌤 にいすけに合う取り入れ方
⭕️目的地なしでOK。近所を歩くだけでも十分。
⭕️「気分がもてば5分だけ」でOK。自由を残す。
⭕️「風・音・光」に意識を向ける“感覚リセットタイム”に。
⭕️帰宅後、「今日の空、きれいだったね」や「どの辺に行ったの?」と自身の頑張りや楽しさを振り返れるように声をかける。
無理なく続けられる“親子のメンタルリズム”が生まれていきました。

⇩各論文で、有効性が説かれています。
うつ病に対する運動療法の有効性 | 新型コロナウイルスや医学・生命科学全般に関する最新情報 | 公益財団法人 東京都医学総合研究所
🚶♂️ 歩き始めてからの変化
最初は渋々。夜の公園を一緒に歩いたり、いずれ居場所の1つにしたら良いかなと思う図書館(徒歩圏内)に一緒に行き下見をしたり。
慎重派HSCの助のにいすけは、【初体験】が苦手なので、一緒に体験することでハードル下げを試みました。
自転車あるし、自転車でウロつけば楽だろうに、

自転車じゃ、途中で帰りたくなった時に折り返しにくいじゃ
小回りが利く【徒歩】が安心らしい😊
でも、ある日こう報告がありました。

片道30分くらいのとこまで行って、折り返してきたよ
その日から少しずつ、一人で外へ出る時間が増えていきました。
歩く距離よりも、「行こうと思えた」ことが何よりの進歩✨️
🚶➡️ウォーキング継続セット👟
せっかく歩くなら、効果を最大限得たい!
負担を減らし、歩数や達成度の記録でモチベーション維持に繋がります😚

🤝 散歩仲間との再会

前よく会ってたおじさんたちと歩いたよ
小学生の時に、散歩してる時に知り合った、【散歩仲間のおじさん】です。
その言葉に涙が出そうでした。
学校ではない“安心できる社会との接点”がありがたい…✨️。
🌼 心の変化と眠りの改善

なんかオレ、前より優しい気持ちでおれる気がする
その一言は、回復の証でした。
たまに食器を洗ってくれたり、弟に優しく接したり。
何だか私には、【出来ることをやった自分への喜び✨️】が溢れているように見えました。
そして夜、毎日ではないものの、自然に眠れることが増えてきています。
🌈 まとめ
「歩くこと」は、心を立て直すリズムになります。
光・風・音の中で、体を動かすことで“回復の回路”が生まれる。
にいすけにとってウォーキングは、再び世界とつながる第一歩でした。今は週に3〜4回徒歩で片道30〜40分かけて図書館へ行き、3・4時間勉強をして、徒歩で帰宅。というサイクルが出来てきました。
図書館が休みだったり、雨天で行けないとウズウズするようで、「夜散歩せん?」と言われたりします。私の都合によって行ったり行かなかったりですが(スマンにいすけ💦)
出来ること・行ける範囲が広がることが喜ばしい今日この頃です😌
医師対応のサービスもあり、心療内科や精神科の受診を迷っている方にも安心です。
継続的にカウンセリングを受けたい方と、目的に応じて使い分けられるのも良いなと感じました😊

定額制で利用しやすく、継続的に心理サポートを受けたい方におすすめです。
医師対応はありませんが、心理師による丁寧なサポートが受けられます😊
💌今辛いあなたへ
今つらい人も、支えている家族も。
今日、ほんの数歩でも前に進めたなら――それはもう、立派な一歩です。
牛歩でも、一歩がミリ単位でも、藻掻いたこと・頑張ったこと・進めたことは事実です。事実を【自分で認める】ことから始められたら良いかと思います。
日常に散らばっている【出来た】に光が当たった時、あなた自身の魅力・価値も輝きを取り戻せるはず。
みんな、日々めちゃ頑張ってる。
このブログに行き着くまでに、沢山検索されたはずです。何かヒントが無いかと行動している証拠です。読んで頂き、ありがとうございます。
私は【自分で選ばせる】と【予め上限を設ける】を主軸ににいすけ関わるように心がけています。
ここまで読んでくれたあなたに、何か贈れるものがありますように。
リアル当事者として、不登校に悩む皆様の回復を切に願う日々です🙏
❀moyu❀
📚参考文献
WHO(2022)/厚労省「こころの耳」/Schuch et al., Am J Psychiatry (2018)
🔗 前回リンクブロック
📖 前回の記事:【前編】不登校の息子に見えた“うつのサイン”──心が弱ったときのSOSを見逃さないために