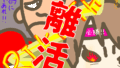🪶はじめに
不登校の息子が、ある日ふとつぶやいた一言。
「オレの人生、意味ない気がする。」
その瞬間、胸の奥が締めつけられました。
私はメンタル系医療施設で仕事をしています。
だからこそ、その言葉が“ただの思春期のつぶやき”ではなく、
心のエネルギーが尽きかけているサインだと感じたのです。
🧩 鬱・適応障害・不登校の関係とは
子どもが「学校に行けない」とき、その背景には“心のエネルギー切れ”が隠れています。
以下の3つはよく似ていますが、実は少しずつ違う特徴を持っています。
🌧 鬱(うつ病)
脳の神経伝達物質(セロトニンやノルアドレナリンなど)のバランスが崩れ、気分の落ち込みや意欲低下が続く。
明確な「原因」がない場合も多い。
朝が特につらく、何をしても楽しく感じられない。
身体症状(頭痛・倦怠感・食欲低下・眠気など)を伴う。
💡ポイント:
病的なレベルの「心のエネルギー切れ」。
努力不足ではなく、脳の不調によるもの。
🍂 適応障害
明確なストレス要因(人間関係・学校・職場など)があり、それに心身が適応できず不安や抑うつが出る。
原因がなくなると回復することも多い。
💡ポイント:
外的ストレスへの反応。放置するとうつ病に進行することも。
🏫 不登校
登校への心理的抵抗が強く、年間30日以上学校を休む。
背景に「適応障害」や「うつ状態」が潜んでいることが多い。
朝の体調不良(頭痛・吐き気など)は心のSOS。
💡ポイント:
「行かない」ではなく「行けない」。
不登校は行動の結果であり、精神的な症状を指す言葉ではありません。心を守るための防衛反応だと言えます。
🔄 3つの関係性イメージ
不登校の背景に「うつ」や「適応障害」が潜んでいることもあれば、
逆に「不登校による孤立・罪悪感」からうつ状態に陥ることも。
つまり、順番ではなく“循環”しているケースが多いのです。

🌧 抑うつとは──“うつ病”とは少し違う「心の疲れ」
私たちは、誰でも落ち込んだり、無気力になったりする時があります。
ただ、それが数日で回復する一時的な“気分の落ち込み”なのか、
それとも脳や自律神経レベルでエネルギーが枯渇している“抑うつ状態”なのか――
この違いを見分けるのは、意外と難しいものです。
💭 「抑うつ」は“うつ病の手前”にある状態
「抑うつ」は、医学的には“うつ病”と診断されるほどではないものの、
すでに脳のブレーキがかかり始めている状態を指します。
つまり、まだなんとか頑張れているけれど、
その“がんばり”が限界に近づいている段階です。
この時期の本人は、よくこう感じます。
「何もしたくないけど、休むのも不安」
「元に戻るために頑張らないと」
「眠っても疲れが取れない」
一見すると“怠けているように見える”この状態こそ、
早期のサインとして見逃してはいけない部分です。
🩶 抑うつのサイン例
抑うつのサイン
| 心のサイン | からだのサイン | 行動のサイン |
|---|---|---|
| 無気力・焦り・自己否定 | 眠れない・朝がつらい・頭痛や胃痛 | 笑顔が減る・趣味への興味が薄れる・外出を避ける |
🌿「心・体・行動」それぞれに表れる小さなサインを見逃さないで。
にいすけもこの時期、
「何をしても意味ない」「前みたいに楽しめない」と言うことが増えていました。
その小さな違和感が、抑うつの始まりでした。
🌿 抑うつと「うつ病」の違い
🌿 抑うつと「うつ病」の違い
| 項目 | 抑うつ | うつ病 |
|---|---|---|
| 主な原因 | 心理的ストレスや環境変化 | 生物学的(脳の機能低下)+心理的要因 |
| 持続期間 | 数週間〜数ヶ月 | 2週間以上かつ日常生活に支障 |
| 回復のきっかけ | 休養・環境調整・カウンセリング | 医療的治療(薬+心理療法) |
| 特徴 | まだ“元気を取り戻せる段階” | 自力では回復が難しい段階 |
🕊 抑うつは「心が少し疲れた状態」。
うつ病は「エネルギーが尽きてしまった状態」。早めのケアで回復のチャンスが広がります。
🌱 親ができるサポート
🌿 抑うつの子への関わり方4つのポイント
① 「怠けてる」と決めつけない
→ 抑うつは、見えない“心の怪我”。
② 安心できる時間を増やす
→ 「今日はこれだけでいいよ」と小さな成功体験を積ませる。
③ 自然と太陽光に触れる機会を
→ セロトニン活性が、抑うつからの回復を助けます。
④ “無理に励まさない”
→ 「頑張れ」は禁句。代わりに「一緒に休もう」で十分。
🕊 無理に元気づけようとせず、「寄り添う時間」こそが回復の栄養です。

💭 息子に見えた“抑うつのサイン”
中学生になって、にいすけの生活リズムは乱れていきました。
環境が変化して、先生との擦り合わせが出来ていなかったこと・同じく不登校の子を持つ親御さん(保育園のお友達だった)から送迎の申し出があって一時的にお願いしていたこと・身体症状が続き、登校出来ない罪悪感が積み重なったこと
などの影響があるかな、と思います。
小学生の頃は登校しない日はウォーキングをしていて、1日8kmも歩くことも。
「ほんまに不登校かい(笑)」と思うくらい、元気でした。
でも中学進学後は、環境変化と心身の負荷が重なり、
“歩くこと”をやめてしまいました。
💬 登校刺激の疲れと「人生意味ない」発言
中学生になり、まだペースも確立していない時期。朝「今日どうする?」と声掛けする(この頃声掛けする日しない日を曜日で固定して、負荷を減らす工夫をしていました=不登校上限設定)中で、
息子は少しずつ疲れ果てていったようでした。
ある日、静かにこう言ったのです。
オレの人生、意味ない気がする。
――その瞬間、私は確信しました。
これは“怠け”ではなく、心のエネルギーが底をつきかけたサイン。
🌙 夜眠れない日々
気分は落ち着いても、夜眠れない。
「眠れん」と言って私の部屋に来る日々が続きました。
私はホットタオルを作り、湯船に浸かる習慣をつけ、ヤクルト1000も導入してみたり(笑)
それでも完全には眠れませんでした。
その時、私はある提案をしました。
身体も頭も、少し疲れてたほうが眠れるよ。ちょっとだけ歩いてみん?
この一言が、次の章(後編)につながっていきます。
この頃1人で家に居ると考え込んじゃう感じだったので、前から悩んでいたペットを飼いだすことにしました🕊️🐤
🌤 まとめ
子どもの「不登校」は、心の状態を映す鏡。
焦らず、まずは“エネルギーの回復”を最優先に。
それが、次の一歩を踏み出すための準備です。
💌あなたへ
「うつ」と「怠け」は違います。
「不登校」は、心を守るための行動でもあります。
次回は、息子が“歩くことで心を取り戻していった”お話をお届けします。
❀moyu❀
🔗 次回リンクブロック
▶ 続きはこちら:【後編】うつ病には歩くことが効く──不登校の息子が“歩く力”を取り戻すまで
医師対応のサービスもあり、心療内科や精神科の受診を迷っている方にも安心です。
継続的にカウンセリングを受けたい方と、目的に応じて使い分けられるのも良いなと感じました😊

定額制で利用しやすく、継続的に心理サポートを受けたい方におすすめです。
医師対応はありませんが、心理師による丁寧なサポートが受けられます😊