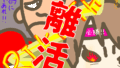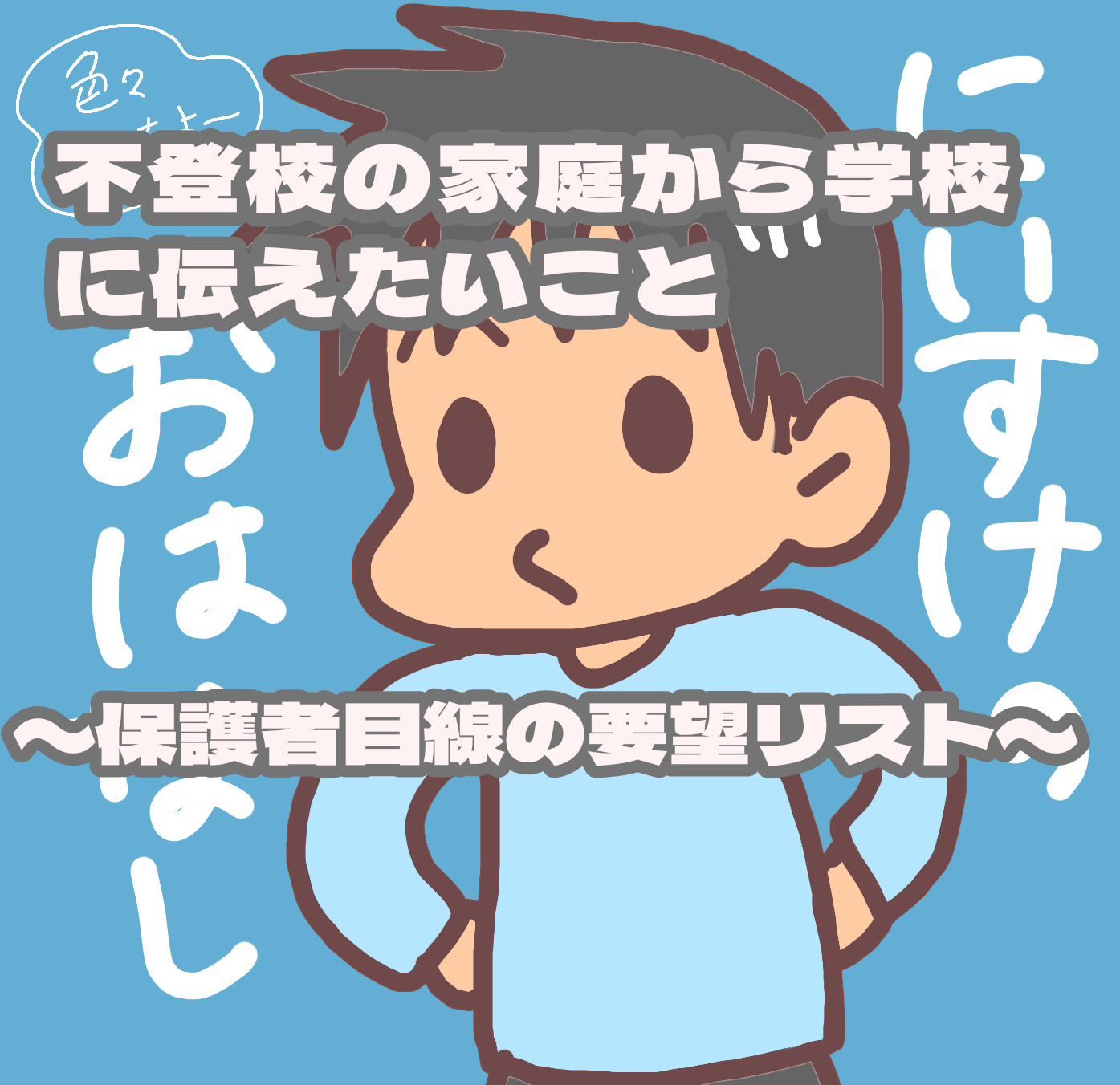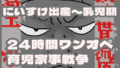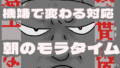不登校が始まったとき、学校との関わりにしんどさを感じたことは多々ありました。
先生方は子どもを気にかけてくれて本当にありがたい。でも実際には、「ありがたさ」と「しんどさ」が表裏一体なんですよね。
ここでは私自身の体験をもとに、保護者として学校に伝えたい要望をまとめました。
同じ立場の保護者が「こう言えばいいんだ」と言葉の参考にしてもらえたら嬉しいです。
1. 負担なら「断っていい」
長男が不登校になった初期、担任+教務主任の先生が、3日おきくらいに電話や家庭訪問をしてくれていました。
最初は「子どもを気にかけてくれてありがたい」と思っていたのですが、夕方の忙しい時間に訪問されても話すことがなく、最後には必ず
「明日はどうかな?」
「待ってるからね!」
と言われ、子どもはプレッシャー、私は「行かせなきゃ」と苛立ち…。
母子ともに消耗していました。

そこで私は思い切って伝えました。
「気にかけていただけるのはありがたいですが、変わりがあればこちらからお伝えするので、今は電話や訪問は控えてください」
するとピタッと止めてもらえて、肩の荷が下りました✨
2. 方針は相談ベースで
不登校の子どもにどう関わるか、学校から一方的に進められるととても負担になります。
電話や訪問の頻度や内容は、最初に親子と話し合って決めてほしいのです。
「学校としてはこう考えていますが、ご家庭の希望も教えてください」
と一言あるだけで、受け取り方は全然違います。
3. 情報をシェアしてほしい
不登校家庭は、他の保護者と繋がりにくく、孤立してしまい情報が不足しています。
だから先生が、校内の他のケース(個人情報は伏せて)や支援機関の情報をシェアしてくれると本当に助かります。
「同じ学年ではないですが、こういうケースがあって、こう対応したら少しずつ前に進めましたよ」
「こういう外部機関に相談してみる方もいます」
そんな一言が、真っ暗なトンネルの中で方向を示す光になります。
4. 子どもの前では“味方”でいてほしい
先生から見れば、不登校の子は「手のかかる生徒」かもしれません。
でも子どもの前では、
「あなたの味方だよ」
「学校は応援してるよ」
という姿勢を示してほしいのです。
無理に登校に誘導するよりも、「味方でいてくれる」という安心感が、自己肯定感を守ります。
5. 担任一人に背負わせなくていい
不登校は今や特別なケースではなく、社会全体の課題です。 だから本来は、担任の先生だけが抱えるものではないと思います。
理想は――
- 校内に「不登校担当」の先生を複数人置く
- 担任はその担当に引き継ぎ、担当が対応(担任とも情報共有)
📝全公立中学校に不登校やいじめ対応専任の「生徒指導担当教員」、文科省が体制強化…来年度から配置 : 読売新聞
⬆️こちらの記事では、今年度から公立中学校へ担当教員の充足を目指すことが書かれて居ます。こうなれば、担任の先生の負担も減り、保護者や子どもも「話が伝わっている安心感」を持てますね。ただ配置するだけじゃなく、中身ある対策であることを祈ります…。

まとめ
不登校は原因も対応も家庭ごとに違います。
だからこそ、「相談ベース」「情報の共有」「子どもの前では味方」 がとても大切です。
学校にとっては大勢の生徒の中の一人かもしれません。
でも、保護者にとってはわが子の人生そのもの。
要望が多く見えるかもしれませんが、どれも保護者の本音です。
この記事が、同じ立場の保護者の方が学校に思いを伝えるときのヒントになれば嬉しいです🌱
❀moyu❀
医師対応のサービスもあり、心療内科や精神科の受診を迷っている方にも安心です。
継続的にカウンセリングを受けたい方と、目的に応じて使い分けられるのも良いなと感じました😊

定額制で利用しやすく、継続的に心理サポートを受けたい方におすすめです。
医師対応はありませんが、心理師による丁寧なサポートが受けられます😊
オススメ記事
⇩不登校の原因について綴ったブログはコチラ⇩