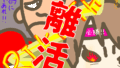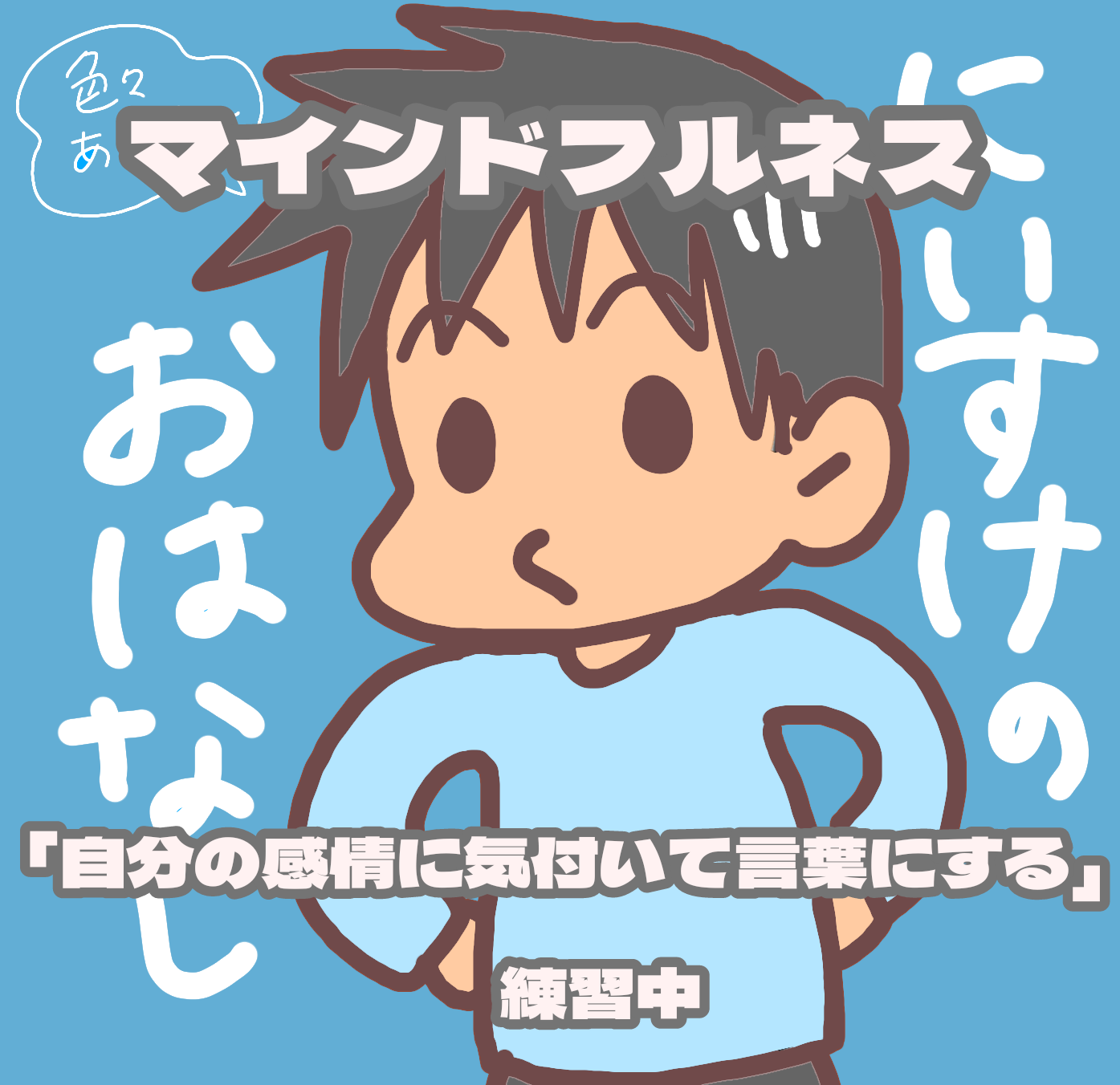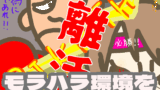〜マインドフルネスって、あとから知ったけど実はもうやってた〜
離婚、不登校、そして感情がうまく分からなかった過去の自分。
今思えば、あの頃の私は
「生きるために感じることを止めていた」のかもしれません。
このブログでは、そんな私がどのようにマインドフルネスに出会い、
不登校の息子とともに
「感情に目を向ける練習」を始めたエピソードを綴ります。
モラハラの渦中では「感情を感じない」ことで自分を守っていた
「いつまで耐えるんだろう、私…」
そうやって、外側から自分を眺めるようにして過ごしていたあの頃。
怒りも悲しみも、感じてしまえば壊れそうで、
“感情にフィルターをかけて”麻痺させていました。
離婚後に感じた「心の穴」
モラハラから抜け出し、自由になったはずなのに…
私の心にはぽっかりと穴が開いたような感覚がありました。
『モラハラ環境に生きた人たち』という本の中で、すとんと胸に入った言葉があります。
「モラハラ環境から脱出したあとこそ、傷は痛みだす」
「感情を麻痺させていた心が、ようやく機能し始めた証拠」
これは、モラハラを受けていた環境から離脱した後に湧き出てくる『強大な不安感』に対する心理士さんの説明です。(モラハラ本についてのブログはコチラ)
安全地帯で心から安心出来て初めて『自分の心』と向き合えるのかな。
まさに欲求5段階説😳
マインドフルネスって、後から知ったけど…実はやってた!
「マインドフルネス」という言葉を知ったのは最近です。
でも振り返ってみると、離婚や不登校という人生の転機において、私は自然とこんなことをやっていました。
- 子どもの今の気持ちに集中する
- 自分の感情に気づき、否定しない
- 「正しいかどうか」ではなく、「心に必要なこと」を選ぶ
これってまさに、マインドフルネスの実践だったんですよね。
簡単にわかる「マインドフルネス」とは?
マインドフルネスとは、「いまこの瞬間」の体験に意識を向けること。
過去の後悔や未来の不安ではなく、
「今、自分が何を感じているか」に気づく練習です。
たとえば…
- 「私は今、不安なんだな」
- 「緊張してるんだ」
- 「泣きたい気持ちがある」
と、自分の感情に名前をつけてあげるだけでも大丈夫◎
息子とのやりとりで学んだ「感情を言葉にする力」
長男は小学5年生の終わりから不登校に。
「学校に行かなくていいよ」と言えたあと、私は彼に「どうしたい?」と聞くようにしました。
でも最初は、「分からん」と答えるばかり。
気持ちが分からないって、実はすごく不安なことなんですよね。
答えやすくなるよう“問い方”を変えてみた
私はこんな工夫を始め
行けなさそう?頑張りたい?って聞くと、少し考えて、ポツリと答えてく
行くかどうか考える日を、月・水・金だけにしてみるのはどう?
火・木はお休みの日って決めて、考えないようにするのもアリだよ
最近しんどいなら、いっそガッツリ休むのも手だよ。
1週間とか、2週間とか、1カ月とか、自分で期間決めてみる?
すると、少しずつですが、にいすけの口から
「こうしようかな」
「今日は休む」
というような言葉が出るように。
自分の気持ちに向き合い始めたサインでした。
親子で「感情の修行中」
今も私たちは、
「自分の感情に気づいて、言葉にする」練習中です。
これは、かつての私自身ができなかったことでもあり、
今こそ向き合い直しているのです。
⇩マインドフルネスについて書いてある記事はコチラ⇩
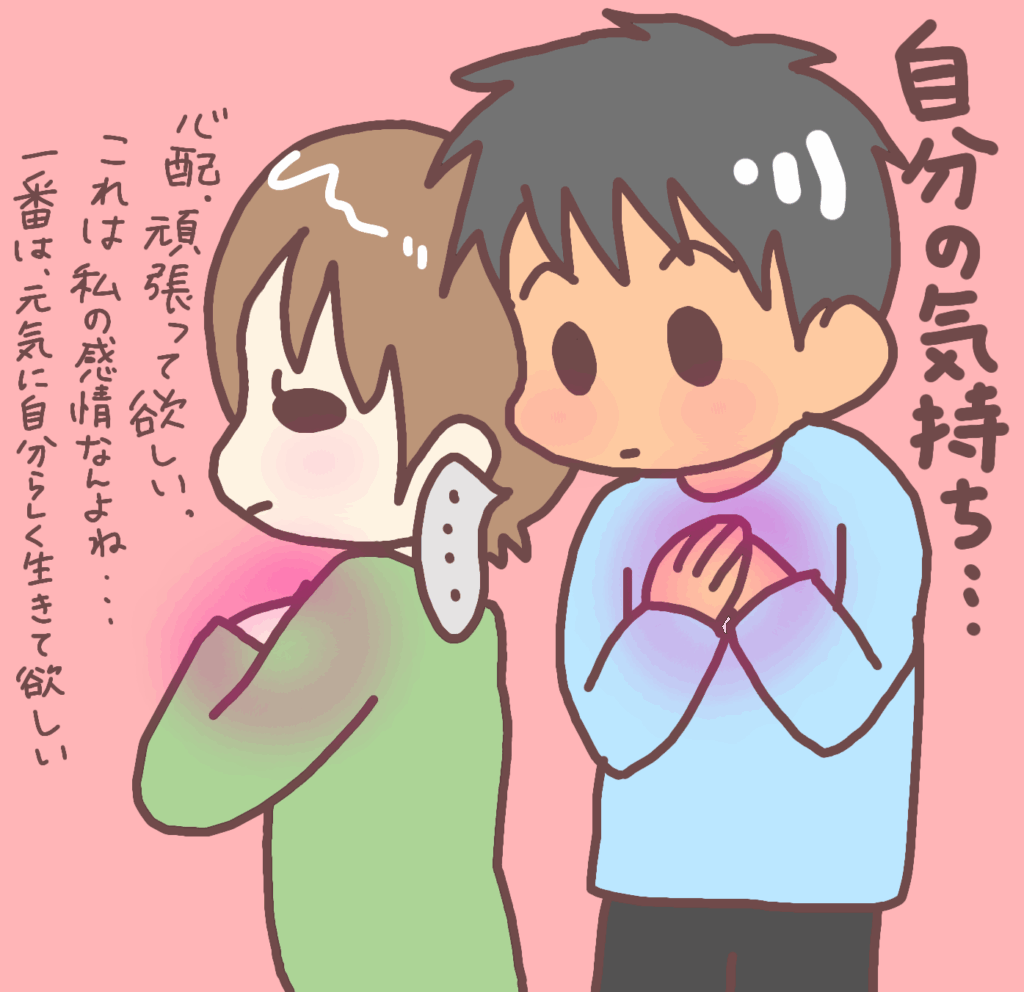
おわりに
マインドフルネスとは、
「がんばる自分をもっとがんばらせる」ためのものではなく、
「今の自分にそっと寄り添う」優しい在り方。
私は、これからも子どもたちと一緒に、
心の声に耳を澄ませながら生きていきたいと思います🌿
あなたへ小さな問いかけ
あなたは今、どんな気持ちですか?
「本当はどう思ってる?」って、自分にそっと聞いてあげてくださいね。
勿論、安心出来る場所で、ですよ😚
医師対応のサービスもあり、心療内科や精神科の受診を迷っている方にも安心です。
継続的にカウンセリングを受けたい方と、目的に応じて使い分けられるのも良いなと感じました😊

定額制で利用しやすく、継続的に心理サポートを受けたい方におすすめです。
医師対応はありませんが、心理師による丁寧なサポートが受けられます😊
⇓オススメ記事⇓
⇩モラハラ環境にいると、自分の気持ちに鈍麻になり言葉にするのが難しくなったりします。そんな時に出会った一冊の本が、私の感じていた違和感や苦痛を代弁してくれたのです(ブログはコチラ)⇩