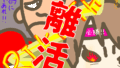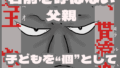最近ふと、保育園の先生から言われたある言葉を思い出しました。
不登校になった長男のサポートを続けてきた中で、私はずっと「信頼」と「本人の選択」を大事にしてきたつもりです。
母である私が一番の味方で
でも、ふと立ち止まったときに、「あの言葉が、私の原点だったのかもしれない」と気づいたのです。
中間反抗期まっさかりの長男
長男がまだ保育園児だった頃。
当時の彼は中間反抗期の真っ只中で、何をするにも「イヤ!」「めんどくさい!」の嵐。ちょっとでも思い通りにいかないと、すぐに投げ出してしまう。挑戦するより先に、イライラして泣いたり怒ったりすることが多く、私もつい「なんでそんなにすぐ諦めるの?」と責めるような言い方になっていました。
正直、どう関わればいいのか分からなくなっていた頃――
担任の先生が静かにこう言ってくれたのです。
「どんな些細なことも、自分で選ばせてみてください」
「自分で選んだことなら、ちゃんとやり遂げたいと思えるんです」
小さな選択でも「自分で決めた」という実感
その日から、私は意識して長男に“選ばせる”関わり方を取り入れるようにしました。
たとえば――
「今日は赤の服にする?それとも青にする?」
「おやつ先にする?それとも宿題終わらせてからにする?」
「先に言いたいことある?それとも、私の話から聞く?」
どれも小さな選択肢だけれど、本人が決めるということを大切にしました。すると、驚くほど反発が減ったのです。
実際に、教育社会学でも「自分で選ぶ経験」が子どもの自己決定感や主体性を高めることが知られています。
こちらのコラムも参考になります⇩
不登校をしてわかった!我が子が不登校になったら親がすること! | パステルジャンプ
もちろん、思うようにいかない日もたくさんありました。
でも、少しずつ「納得して動く」「やり遂げようとする」姿が増えていったように思います。
「分からん」って言うこともある。でもそれでいい
うちの子は、たぶん私の血をしっかり引いていて(?)
優柔不断なところもあって、「どっちでもいい」「分からん」ってなることも多いです。笑
たぶん、選ぶことそのものに迷いが出やすい性格なんだと思います。
だから無理に「自分で決めてよ!」とは言わずに、
2択に絞ったり、「Yes/No」で答えられるようにしたりと、選びやすさを整える工夫をしています。
この関わり方は、発達支援の現場でも有効とされています。
優柔不断な子どもには選択肢を減らし、答えやすさを保証することで「自分で選ぶ力」が育ちやすいと言われています。
⇩様々なコラムでも、『本人に選択させることの重要性』が述べられています。⇩
「自分で決められない」優柔不断な子供の心理と育て方|CHANTO WEB
自分で決められない…いつも悩んでしまうHSCの子どもが決める力をつける2ステップ | パステルジャンプ
それでも迷ってしまうときは、
「どっちか選ばないといけないってことはないよ」
「後で決めても大丈夫だよ」と伝えて、
“選ばない自由”も大切にしています。
不登校の支援にもつながっていた
小学校高学年で完全不登校になった長男。
彼の気持ちをどう支え、どう前に進めばいいのか、模索の日々でした。
そんな中でも私が一貫して大事にしてきたのは、「本人の気持ちを尊重し、選択の主体を渡すこと」でした。
たとえば、学校との面談には長男も一緒に参加させました。
「お母さんだけで来てください」と言われることもあったけれど、私は「本人不在で話を決めるのは違う」と感じて、あえて連れていきました。
先生たちとの会話の中で、言語化が難しそうな場面では少しサポートしつつ、
「自分でどうしたいか」
「今日はここまでにしたい」
「この話はしたくない」
といった気持ちは、なるべく本人が言えるように環境を整えました。
このような「本人の意見を尊重する支援」は、文部科学省の報告書でも強く推奨されています。
たとえば令和4年の「不登校児童生徒への支援の在り方について」では、“本人の意思や希望を尊重し、本人参加型の支援体制を構築する必要がある”と明記されています。
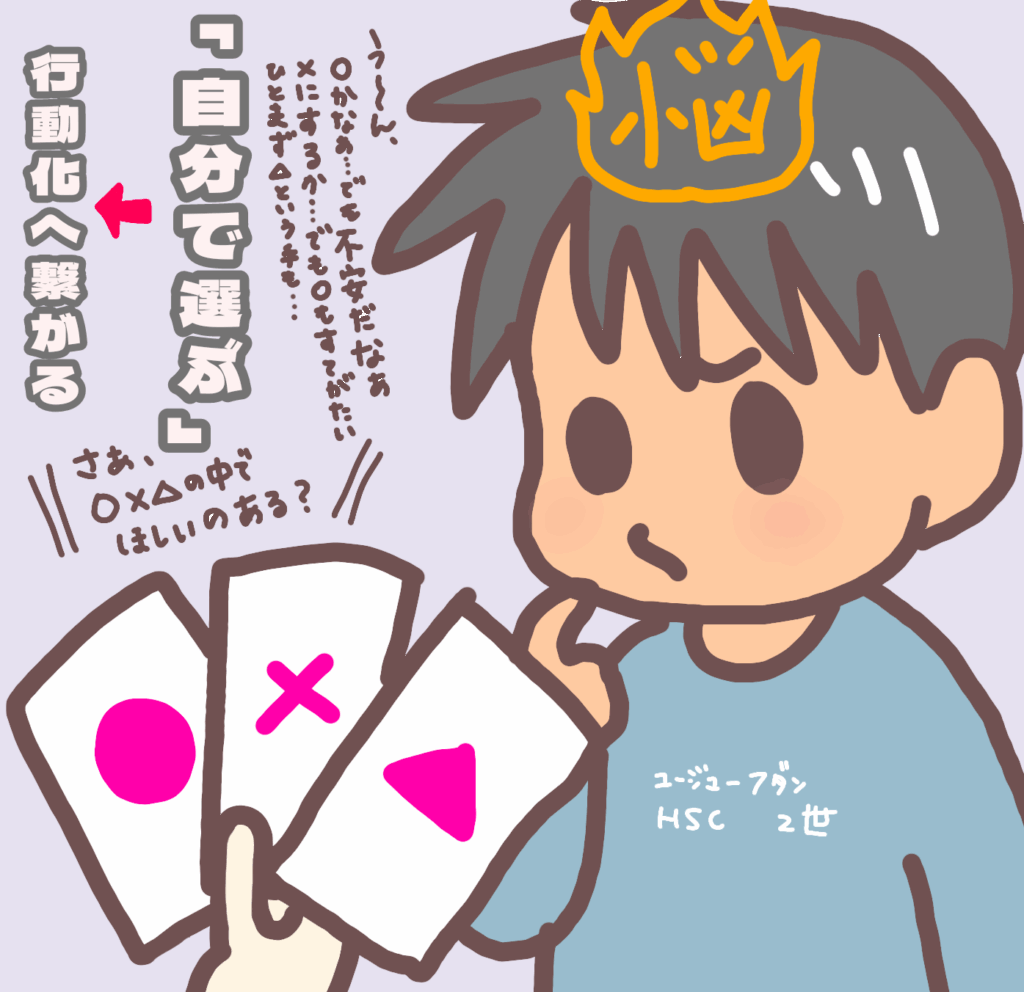
それは「自分の人生を自分で決めていいんだよ」という、私からのメッセージでもありました。
違う人格、違う人生を生きている子どもだから
親子とはいえ、子どもは自分とは違う人格で、違う人生を生きている存在です。
「親の思うベスト」を押しつけるのではなく、「この子自身がどう生きたいか」を見つけていけるように寄り添いたい――そう思っています。
だからこそ、学校と口裏を合わせて無理に誘導したり、「騙し討ち」的な方法は絶対に避けたかった。
揺らぐこともあったけど、越えてはいけない一線があると信じて、関わってきました。
忘れてしまう日があっても、思い出して初心に返る
…なんて、偉そうに言っているけれど、
もちろん私も、すっかり忘れていた時期もあります😅
「早くして!」「なんで決められないの?」と急かしてしまったり、
「もう、知らんよ!」と投げやりになってしまったことも、正直たくさんあります。
でも、そんなときにふとあの先生の言葉を思い出して、
「そうだった、私は“信じる”って決めてたんだ」って初心に返る。
それだけで、子どもとの向き合い方が、少しだけやさしくなれる気がします。
医師対応のサービスもあり、心療内科や精神科の受診を迷っている方にも安心です。
継続的にカウンセリングを受けたい方と、目的に応じて使い分けられるのも良いなと感じました😊

定額制で利用しやすく、継続的に心理サポートを受けたい方におすすめです。
医師対応はありませんが、心理師による丁寧なサポートが受けられます😊
🪶まとめ
子どもが「自分で選んだ」と感じることで、納得して行動しやすくなる
優柔不断でもOK。選択のハードルを下げる工夫が大切
思い出せることが大事。初心に返るたび、よりよくしようという行動が積み重ねられていく。
いつも絶え間なくなんて私には無理😅だけど、学んで行動して、また思い出して実行することは出来る。いつからでも。
あの日、保育園の担任の先生が教えて下さった学びは、保育だけじゃなく、人を育てるのに必要不可欠な視点でした。
同じく優柔不断っ子の親御さん、伸びしろしかない『子(人)育て』の視点がお役に立てたら嬉しいです😌
❀moyu❀
⇩オススメ記事⇩
自分の心の声を聴く、マインドフルネスのブログはコチラ⇩