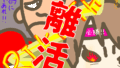SNS上で、不登校の親子に向けて
「なんで学校に行けないの?」「親の育て方じゃないの?」
といったコメントを見るたび、無力感と怒りとがごちゃまぜになります。
中には本当に理解しようとしてくれる人もいる。でも大半は、理解する気なんてない。ただの興味本位だったり、相手の正しさを証明したいだけの「問い」だったりします。
本当に知りたいなら、もっと違う聞き方があるはずなんです。
たとえば「何があったのか、良かったら教えてくれませんか?」といったような。
今回は、不登校の子どもを育てる親として、日々感じる「説明疲れ」と「社会の圧力」について、ありのまま綴ります。
■ 話が通じない。でも、お互い様…なのか?
SNSを見ていると、本当に話が通じない人が多いなと思います。
たぶん、私も“通じない側”と思われているんでしょうけど。
でも、無関係な他人の不登校にマウントをとって、煽って、反論したら「ヒステリック」だとか「変わってる」だとか…😑
それって、どこに着地したいんでしょうね。
「なんで?」と聞いてくるけど、結局聞く気がない。
それが一番、心を消耗させます。
■ 「説明してよ」に応える気力なんて、もう残ってない
聞く気がない人に、あの膨大な経緯を、今すぐ、分かりやすく、相手が納得する形で説明するなんて、無理です。
仮に私が平穏な精神状態だったとしても、相手が“納得するための説明”をヒマラヤ級のハードル越えて伝えるスキルなんて、ありません。
しかもこちらは、毎日が見えないトンネルの中で、子どもの不安と、自分の焦りと向き合っている。
📊 文部科学省の調査によると、不登校の子どもをもつ保護者は「学校の理解・支援の乏しさ」「周囲の偏見や誤解」が大きな負担と感じているそうです。
(文部科学省 令和5年度調査報告書PDF より)
それだけで、もう限界ギリギリ。
「説明しないのは怠慢だ」と言われたところで、もはや返す気力も出てこないのが現実です。
■ 精神的に削られている親は、反論すらできない
不登校の子を育てていると、日々のちょっとしたことでも気力が削れていきます。
(※登校しているお子さんの親御さんが楽だと言いたいのではありません。それぞれ違う重圧があることを、まず前提においてください)
ただ、不登校親には、立場になってみないと分からない種類の「重さ」があります。
💭「分かってもらえない苦しみより、“分かろうとされない苦しみ”の方が深く刺さる」
という言葉を、私は最近すごく実感しています。
重たい鉛を抱えた状態で、瞬発力も落ちるし、反論力も残っていません。
これは、精神的に追い詰められたときにパフォーマンスが落ちるのと同じです。
■ 「わかって」とは言わない。でも、「傷つけないで」とは言いたい
正直なところ、反論しようとしても、届かないことが多すぎて(他の方のやり取りを見て)諦めてしまいます。
多数の同調者を引き連れて、上から「評価してやる」「正してやる」と言うかのような態度にさらされて、世の中が怖くなる瞬間もあります。
でも、一部にはちゃんと話を聞こうとしてくれる人もいます。
その存在が、どれだけありがたいか…。本当に救われます。
私も以前、たまらずコメント内でやり取りした方が居ました。その方は真剣に話を聞いてくれました。でも、「不登校=将来ニート」という固定概念が変わることは無く、『見ず知らずのその方に分かるように、私の中のモヤモヤを伝える』という気力は起きず、静かにフェードアウトしました…。
こういうこと、多いと思います。声を挙げる気力の無い当事者に比べて、体験もせず、傷つくリスクの無い場所から発信する人の方が多いから。多勢に無勢(「「多数の勢力には対抗できない」「大勢には逆らえない」)になりやすい構図かなと思います。
私は、「わかってほしい」ではなく、もうすでに傷付き疲弊している人に「追い打ちをかけないでほしい」と伝えたい。
どうか、不登校親の心の奥にある苦しみを、軽んじないでください。
あなたのその「一言」が、
ギリギリの心を壊すこともある。

【まとめ】
この文章を読んで、もし少しでも「そうだったのか」と感じてくれたなら、それだけで意味があります。
そして同じように、声を上げる余裕すらないほど疲れた親御さんへ。反論できないのは、弱さじゃない。
それは、真剣に子どもに向き合ってきた証。誰かの“正論”に折れそうになる日もあるけれど、あなたの在り方は間違っていません。
期待を裏切られてばかりなら、もう期待しなくていい。
外の声が遠くに感じるなら、心のシャッターを閉じたっていい。
それよりまず、自分と子どもを守ること。そのための「線引き」は、わがままじゃなく、生きるための知恵です。
noteにて、『母親のせい』になりやすい理由がまとめられている記事を見つけました。
➡️コチラ
母親が子供の一番近くで支えてる家庭が多いからこそのイメージですね。
オススメ記事⇩
『体験』が、言葉に『深み』『重み』『共感』を持たせる。説得力のある【うまくいかなかった体験】をブログに綴りました。