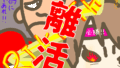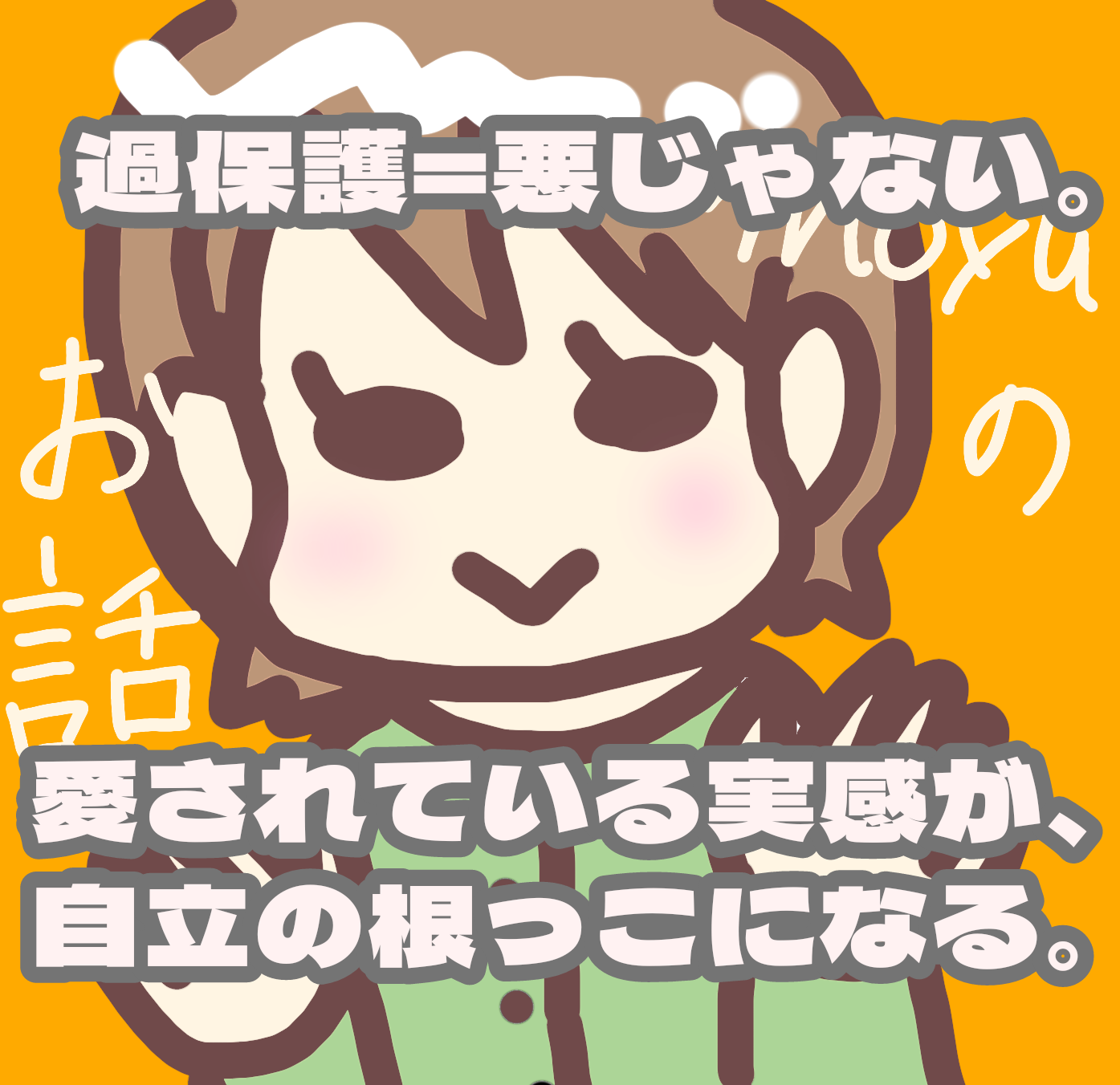―支える側だった私が、支えられる側になったとき―
医療従事者として、私は日々「心が疲れた人たち」と向き合っています。
うつ病、不安障害、統合失調症──
「もう頑張れない」と語る人に、「大丈夫ですよ」「無理しないで」と声をかけてきました。
しかしそんなある日、自分の息子が学校に行けなくなったとき、私はどうしていいか分からなくなりました。
「知識がある私」でも、動揺した
私は、精神科医療の知識があります。
人の心がどれほど繊細で、傷つきやすく、そして“目に見えない不調”がどれほど重いかも知っていました。
頭では理解していたんです。
「無理させてはいけない」「休んでいい」と。
それでも、実際に自分の子どもが「学校に行けない」と口にしたとき、
私は大きく動揺しました。
「どうしよう」
「なんとか戻さなきゃ」
「このままで大丈夫なの?」
「この子の将来は?」
そんな不安が一気に押し寄せてきて、
メンタル医療に関わってきた私の知識は、母としての感情の前でかき消されていきました。
仕事の知識があっても、我が子の危機には激しく動揺するし、
頭でわかっているはずの言葉掛けができない。
言いなじみのある私も、我が子には「ただの母親」でしかなかったのです──。
「休んでいいよ」の重み
私はこれまで、何人もの患者さんにこう言ってきました。
「無理しないでくださいね」
「頑張らなくていいですよ」
「今は休むときです」
でも、いざ自分が“支えられる側”になって、初めて気づいたんです。
その言葉は、思っていたほど優しくなかった。
「いいよ、いいよ。休めばいいじゃん」
そう言ってくれる人の言葉が、時に突き放すように感じました。
確かに、善意ではある。
でも、その言葉には“責任”がないんです。
そのあとどうなるかまでは考えていない、
言って終わりの「他人事のようなやさしさ」。
それがすごく空しくて。
「この先どうするのか」「じゃあ、何を支えにすればいいのか」
そこまで一緒に悩んでくれる人は、ほとんどいませんでした。
「支える」って何だろう
医療現場では、「相手のペースに寄り添うこと」「その人の中にある力を信じること」が大切だと学んできました。
けれど、家庭ではそれがうまくできなかった。
だって私は「母親」だったから。
この子の未来を守らなきゃと、どうしても“答え”を探してしまう。
本当は、「答えなんてない」状況で、ただ一緒にいることが一番の支えだったのに。
知識があっても、うまくできなかった。
悔しくて、自分を責めたし、たくさん泣きました。
行けないことは「弱さ」じゃない
医療の現場でもよく聞きます。
「もっと早く限界に気づけたらよかった」
無理して、我慢して、頑張りすぎた結果として、心が動けなくなってしまう。
息子の不登校も、もしかしたら「その前の段階」だったのかもしれません。
動けなくなる前に、「自分の限界」にちゃんと気づけたこと。
それは“弱さ”ではなく、“命を守る力”だったのだと思います。
そして私は思うのです。
「厳しさ」や「しつけ」だけが、子どもを強くするわけではないと。
実際、私が出会ってきた子どもたちの中には、
「ちょっと過保護じゃない?」と思うような家庭で育った子が、
しっかり自分の気持ちを言葉にできて、自分の意思で道を選べる姿を見せてくれたことが何度もありました。
きっとその子は、十分に守られてきたからこそ、自分の力で立ち上がる勇気を持てたのだと思います。
「子どもは、十分に守られた経験があってこそ、自分の力で立ち上がる勇気を持てる」
― ドロシー・ロー・ノルト
一方で、「厳しく育てないとワガママになる」と信じて、
無理に“強くあれ”としつけられてきた子ほど、
本音を言えず、心の声を押し込めてしまうこともあります。
「厳しすぎるしつけは、子どもに『自分は無力だ』という学習をさせてしまうことがある」
― アルフレッド・アドラー
✅️アドラー心理学についてはこちら
「甘やかされた子が弱くなる」のではなく、
「愛されなかった子が、自分を見失ってしまう」──
そんな現実も、私は現場で何度も見てきました。
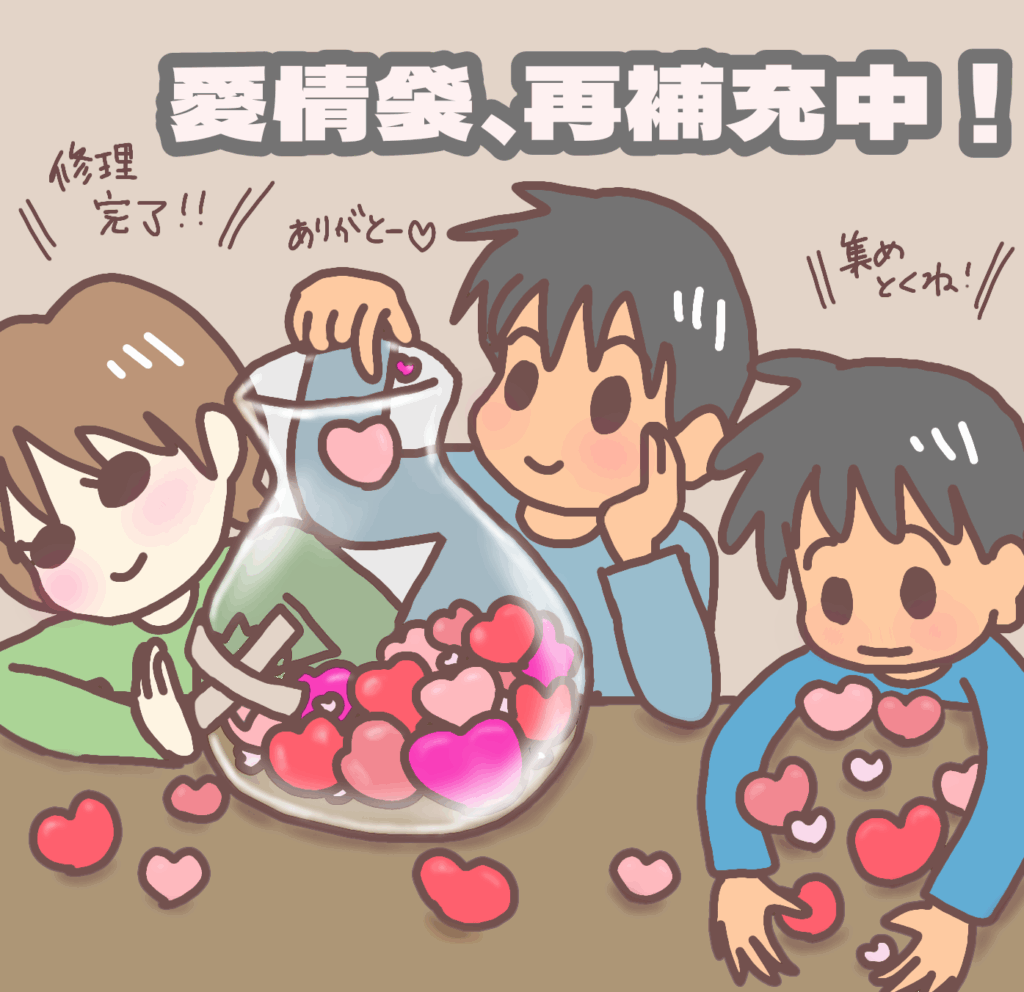
「生きる力」を支えるということ
学校に行かなくても、社会にはたくさんの道があります。
でも今の社会はまだ、「行かない選択」に不寛容です。
「普通」に戻そうとする圧力があまりに強い。
でも、私は声を大にして言いたい。
行かなくても、生きていける。
学校に行けないのは、人生の終わりじゃない。
むしろ、そこから始まる新しい生き方がある。
いま、私が伝えたいこと
私たちは、「自立させるために厳しく」と思いがちですが、
本当に大切なのは、“自律”できる力を内側に育てること。
そのためにはまず、「無条件に受け入れてもらった」という安心感が必要なんですよね。
「“自律”は、“自立”の前にある。心の声を尊重されて育った子ほど、社会で自分の足で立てる」
― 佐藤学(教育学者)
私はこれからも、医療者として人を支えていくし、
母として子どもを支え続けていきます。
支える側でもあり、支えられる側でもある──
その両方の立場を経験して、ようやくわかったことがあります。
言葉には、責任がある。
やさしさには、覚悟が必要。
そして何より、
「あなたのままで大丈夫」だと心から思えること。
それこそが、人の心を支える最初の一歩なんだと思います。
医師対応のサービスもあり、心療内科や精神科の受診を迷っている方にも安心です。
継続的にカウンセリングを受けたい方と、目的に応じて使い分けられるのも良いなと感じました😊

定額制で利用しやすく、継続的に心理サポートを受けたい方におすすめです。
医師対応はありませんが、心理師による丁寧なサポートが受けられます😊
最後に
不登校になった息子は、今も家で過ごしています。
完全に元気になったわけじゃないけれど、
少しずつ、自分のペースで世界を見ようとしています。
私は、そんな息子の歩幅に合わせて、ただそばにいることに決めました。
かつての私のように、今悩んでいる親御さんや子どもたちに、
この言葉を届けたいと思っています。
大丈夫。あなたは、あなたのままでいい。
オススメ記事⇓⇓⇓
✅️息子が不登校になってやっと向き合えた「特性」。良かれが彼を苦しめていた。そんな経過をこちらの記事で綴りました。⇩
✅️限界突破した後、「日常」を「頑張り続ける」が、いかに難しいか・イベント「だけ」なぜ参加出来たのかをこちらの記事で綴りました。⇩